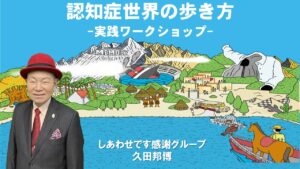「どんな薬剤師になりたいか」悩む薬学生へ。がんサバイバー講師が語る未来の創り方

「どんな薬剤師になればいいのか、将来が不安です」 「キャリアビジョンが描けません」
先日、薬学部の大学講義に登壇した際、学生の皆さんからこのような「キャリア」に関する質問を多くいただきました。
この記事では、なぜ私が講義の「満足度」にこだわるのか、そして「患者として生きる薬剤師」の視点から、未来の薬剤師たちに伝えた「キャリアを考える上で最も重要な2つの視点」を解説します。
講義の「満足度」は事前質問で決まる
私は大学講義の前には、学生から必ず「事前質問」を頂くことにしています。
そして、直前に頂いた質問への回答を、講義の本編の中に埋め込む形で準備します。 講師が「話したいこと」を一方的に話すのではなく、受講者が「聴きたいこと」を聴ける。
この「双方向性」こそが、講師と受講者双方の満足度を最大化する鍵だと、800回以上の講演経験から確信しています。
私が伝えた「未来を創る」ための2つの視点
今年の薬学部では、特にキャリアに関する質問が散見されました。 白血病を経験し「患者として生きる」私が、薬剤師のキャリアについて学生に伝えたのは、以下の2つの視点です。
1. キャリアビジョンを描くこと
まず、自分自身が「どのような薬剤師になりたいのか」というビジョン(羅針盤)を持つことです。
「病院か、薬局か」といった「場所」の選択ではありません。 「患者さんの不安に寄り添える薬剤師になりたい」 「在宅医療で、多職種連携のハブになれる薬剤師になりたい」
私自身、「患者」になったことで、製薬会社にいながら「医療現場のコミュニケーション」を改善するという強いビジョンが生まれました。ビジョンがあれば、困難な時でも道に迷いません。
2. 世間の動きを把握し、未来を「創造」すること
次に、世間の動き(社会情勢、AIの進化、医療制度の変化)を常に把握し、未来を「予測」するのではなく「創造」する意識を持つことです。
これからの時代、「処方箋通りに薬を出す」だけの薬剤師はAIに取って代わられるかもしれません。 しかし、「患者の不安」を傾聴し、「コミュニケーション」で信頼関係を築く仕事は、人間にしかできません。
世の中の変化を恐れるのではなく、変化を読み解き、「自分なら、この変化の中でどんな新しい価値を生み出せるか?」と考える。その「未来を創造する視点」を持つよう回答しました。
この2つの点(ビジョンと創造)だけでも、一つの講義ができます。 未来を担う学生たちに、私の経験が少しでも役立てば幸いです。
しあわせです💖感謝
薬学生・若手薬剤師の「キャリア教育」ご担当者様へ
「自分はどんな薬剤師になるべきか?」 多感な学生・若手の時期に、当事者(患者)であり、社会人(薬剤師)でもある講師の「生の声」を聞くことは、彼らのキャリア観に最も強く響きます。
久田邦博の「キャリアビジョン研修・講義」は、単なるスキル研修ではなく、医療者としての「働く意義(ビジョン)」を自ら見つけるための“火付け役”となります。