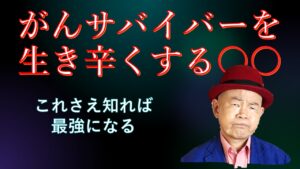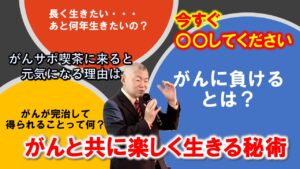生き辛さはなぜ起きるのか?【がんサバイバーへの偏見とレッテル】
【がんサバイバーへの偏見とレッテル】
「がんの治療は終わったはずなのに、なぜか社会で“生き辛さ”を感じる」 「良かれと思ってかけた言葉が、サバイバーの方を深く傷つけてしまった」
がんサバイバー(当事者)も、そのご家族、医療従事者、ピアサポーターも、こうした「見えない壁」に悩むことがあります。
その「生き辛さ」の正体は、多くの場合**「アンコンシャスバイアス(無意識の偏見)」**、つまり悪意のない「思い込み」や「レッテル貼り」です。
この記事では、私自身の22年間のサバイバー生活で直面してきた事例を共有し、どうすればその苦しみから解放されるのか、その具体的なヒントを解説します。
1. なぜ起きるのか?:「無意識」だからこそ厄介な偏見
アンコンシャスバイアスは、「無意識」の思い込みであるため、なくすことはできません。 大切なのは、「自分は偏見を持っていない」と思うことではなく、「自分も必ず持っている」と気づき、意識することです。
特に医療者や支援者は、無意識のうちに**「自分の思い込みの世界」**に、当事者を導こうとしていないでしょうか?
2. 具体例:「良かれと思って」がサバイバーを苦しめる
私が22年間で体験してきた「無意識の偏見(レッテル)」には、例えば以下のようなものがあります。
-
「がんサバイバーだから、お酒や旅行は控えるべきだ」(行動の制限)
-
「がんになったんだから、人生観が変わって『丸くなる』べきだ」(人格の決めつけ)
-
「サバイバーなのに、そんなに元気に振る舞うべきではない」(感情の制限)
-
「がんになったんだから、もう〇〇(仕事、出産など)は諦めるべきだ」(可能性の否定)
これらはすべて、「サバイバーはこうあるべきだ」という支援者側の「無意識の思い込み」が生んだ言葉です。
3. どうすればいいのか?:「患者」ではなく「一人の人」として見る
では、どうすればサバイバーを苦しませずに済むのでしょうか。 解決策は、驚くほどシンプルです。
それは、がんサバイバーを「患者」と見るのではなく、「一人の人」として見ることです。
「病気」という側面だけでその人を判断するのではなく、その人固有の「個性」や「人生」に目を向けてください。
そして、彼らが送っているのは「療養生活」ではなく、私たちと同じ「日常生活」であると意識することです。「日常生活」の中で、仕事もすれば、遊びもすれば、悩みもします。
「がんサバイバー」というレッテルを外し、「〇〇さん」という一人の人間として接すること。それだけで、サバイバーの「生き辛さ」は劇的に軽減されます。
4. すべての人が「偏見」を持っていると自覚する
最後に重要なのは、このアンコンシャスバイアスは、医師、看護師、薬剤師、ピアサポーター、そして、がんサバイバー自身も持っているということです。
サバイバー自身が「がんになったから、もう〇〇はできない」と自分の可能性にレッテルを貼ってしまうこともあります。
すべての人が「自分も無意識の思い込みを持っている」と意識し、お互いに「一人の人」として接するように心がけてください。
しあわせです❤感謝
その「無意識の思い込み」、研修で「気づき」に変えませんか?
「良かれと思って」かけた言葉が、患者さんやサバイバーを無意識に傷つけているかもしれません。
久田邦博の「医療接遇研修」や「講演」では、本記事のような“当事者の生の声”をベースに、医療者や支援者自身が持つ「アンコンシャスバイアス」に気づき、明日からの行動を変えるためのワークショップを行います。
「患者」ではなく「人」として向き合うチーム作りの第一歩として、ぜひご相談ください。
→ 【無料相談】「アンコンシャスバイアス」に気づく研修・講演はこちら