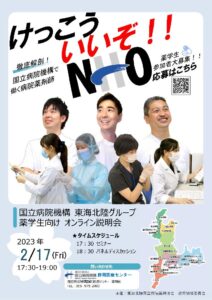「グループ・ピアサポート」が行動変容を起こす科学的理由。認知症当事者・丹野智文さんとの対話から
「免許返納をしたほうがいい」「もっとこうしたほうがいい」
家族や医療従事者がいくら正論を伝えても、当事者の行動はなかなか変わりません。
しかし、同じ境遇の「仲間」の中に入ると、驚くほど自然に行動が変わることがあります。
昨日は、中区認知症フォローアップ講座に参加し、
若年性認知症の当事者として活動される丹野智文さんのお話を聞きました。
そこで確信したのは、**「グループ・ピアサポート(集団での相互支援)」**こそが、
個人のピアサポートを超えて、人の行動を変える最強の手法ではないかという点です。
丹野智文さんとの共通点と親近感
丹野さんとは、私が2018年に講演会を企画した時に知り合いました。
人生の転機(発症)を迎えた年齢が同じ30代後半であること、
小さな子供がいること、元営業職であること、
そして自己開示して講演活動をしていることなど、
多くの共通点があり、勝手ながら強い親近感を感じています。
実は、この時の講演会こそが、
私が「若年性認知症本人家族交流会 あゆみの会」に関わるきっかけにもなりました。
なぜ「グループ」だと行動変容が起きるのか?(行動心理学の視点)
(本文) 昨日の講演で最も関心を持ったのが、「グループ・ピアサポート」の効果です。
認知症の方が集まって話し合いをしていくと、
誰に強制されるわけでもなく、本人の意思に基づいて行動変容が起きていくのです。
症状が進行した時の対策
免許返納の決断
道に迷った時の対応方法や、買い物の工夫
私は現在、行動心理学を用いた研修プログラムを作成していますが、
これはまさに**「社会規範(Social Norms)」というナッジ(行動を促す仕掛け)**が働いていると感じました。
「仲間がやっているから、自分もやってみよう」
「あの人が楽しそうにしているから、自分もできるかもしれない」
仲間の行動がモデルとなり、新たな当事者に好影響を与える。
これは、家族や医療従事者が「説得」するよりも、はるかに強力に行動変容を起こします。
がん患者も同じ。「止まり木」で起きる変化
これは認知症に限った話ではありません。
私が運営する「がんサポ喫茶 止まり木」というがん患者のグループ・ピアサポートでも同じことが起きています。
「がん患者同士だから納得できる」
「あの人の真似をしてみたい」
がん以外の共通項は無いにもかかわらず、一緒に居て楽しく、自然と前向きな変化が生まれていくのです。
以前、精神障害の方のフットサル練習を見学した時もそうでした。
薬剤師として病院で見ていた世界とは全く異なり、
誰もが活き活きとしてプレイしていました。
あれもまた、スポーツを通じたグループ・ピアサポートの力です。
診断を受けたら、迷わず「仲間」の中へ
グループ・ピアサポートは、1対1のピアサポートよりも、
さらに多角的な視点と「社会規範」の力が働くため、有効な手法であると再認識しました。
もし、若年性認知症の診断を受けたら、出来るだけ早く「あゆみの会」に参加されることを願います。
そして、がんの診断を受けたなら、私たちの「止まり木」に来てください。
迷わず今すぐ、仲間の中に飛び込んでみてください。
そこには「生きた教科書」がたくさんあります。
しあわせです感謝
仲間がいれば、行動は変わる。人生も変わる。
一人で悩まず、まずは同じ境遇の仲間がいる場所にアクセスしてください。
【がん患者・ご家族の方】
私たちが運営する「がんサポ喫茶 止まり木」でお待ちしています。
【若年性認知症と診断された方】
「あゆみの会(名古屋市認知症相談支援センター)」へお問い合わせください。