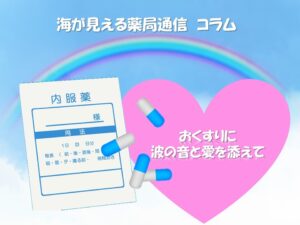認知症支援の第一歩。「アンコンシャスバイアス(無意識の偏見)」に気づく実践ワークショップ【研修レポート】
「認知症サポーターを増やしても、現場の理解がなかなか深まらない」 「『認知症=怖い、大変』というメディアが作った偏見が、支援の壁になっていないか?」
認知症支援の現場で、そんな課題を感じていませんか?
多くの支援者が、自分でも気づかない**「アンコンシャスバイアス(無意識の偏見)」**を持っています。この記事では、名古屋市いきいき支援センターで導入された、その「偏見」にまず気づき、当事者の世界を体感する新しい実践ワークショップについて解説します。
課題:「認知症サポーター」が持つ“無意識の偏見”
今月から名古屋市内いきいき支援センター(地域包括支援センター)からの要請で、「認知症サポーターステップアップ研修」を数回担当しています。
推進員の方との打ち合わせで浮かび上がった現時点での課題は、**「多くの方が持つ認知症へのイメージは、マスメディアからの影響を強く受けている」**という点でした。
これは、本人も気づいていない「アンコンシャスバイアス(無意識の偏見)」であり、このバイアスに気づかない限り、本当の意味での支援や共生は始まりません。
解決策:当事者視点の前に「自分のバイアス」に気づく
そこで私は、従来の「認知症世界の歩き方実践ワークショップ」が最適だとお勧めしました。
ただし、私が提供するのは独自のオリジナルプログラムです。
まず、**「①アンコンシャスバイアスに関するワーク」を行い、自分自身の偏見が当事者の生活にどのような影響を及ぼすのかを考えます。その上で、「②本編(当事者の中で起きている世界の体感と、具体的な対応を話し合うワーク)」**に入る二段構えの構成にしています。
偏見に気づいてから当事者の世界を学ぶことで、知識が「自分ごと」として深く落とし込まれます。
目指すもの:認知症だけでなく「共生社会」の実現へ
このワークショップの直接の目的は「認知症になっても安心して暮らせるまちづくり」です。
しかし、この「無意識の偏見に気づく」というプロセスは、認知症に限った話ではありません。
がんになっても、障害を持っても、高齢になっても——。誰もが安心して暮らせる「共生社会」の実現こそが、私の目指すゴールです。応援よろしくお願いします。
しあわせです❤感謝
「偏見」が支援の壁になっていませんか?
「認知症サポーターを養成したものの、地域住民やスタッフの意識が変わらない」 「『認知症=怖い』という“無意識の偏見”を何とかしたい」
久田邦博は、ファシリテーションと「当事者視点」を活かし、「アンコンシャスバイアス」に気づき、行動変容を促す研修を設計します。
#認知症世界の歩き方ワークショップ #認知症サポーターステップアップ研修 #アンコンシャスバイアス #共生社会 #認知症地域支援推進員 #地域包括支援センター #しあわせです感謝