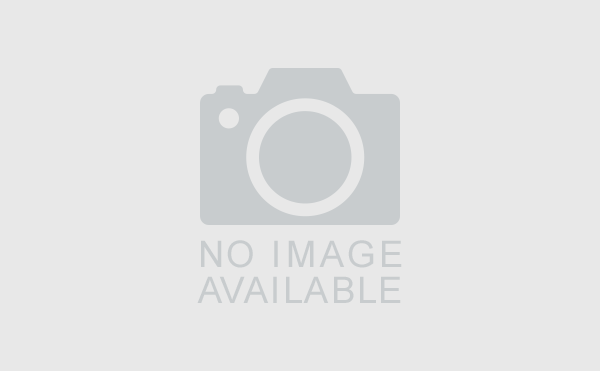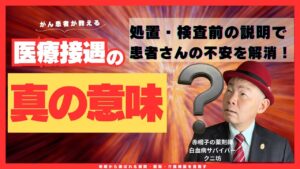認知症で独居の方」の在宅退院をどう実現する? 支援の壁を壊す“多職種連携”の具体策
「認知症で独居の方の在宅退院」は、医療・介護連携において最も困難なテーマの一つです。
「誰がどこまで支援するのか?」「本人の意思は?」——多くの課題があり、多職種間の連携がうまくいかず、退院支援が難航するケースは少なくありません。
この記事では、先日、地域包括支援センターで実施したワークショップ「認知症の世界の歩き方」の実例をもとに、この困難な課題に対して、ファシリテーション(対話促進)を用いてどのように具体的な行動計画に落とし込んでいったかを解説します。
「独居で認知症のある方が在宅退院に向けてどのような連携が可能か」
「その人らしく安全に暮らすために各立場でできること」
第214回 三方よし研究会に参加し
グループディスカッションの内容を発表する機会を頂けました。
「その人らしく安全に暮らすために各立場でできること」でした。
以下が私のグループで討議した内容です。
認知症でパニックを起こしやすい方の対応
最初はそのパニックに関して傾聴していき落ち着いてもらうというご報告でしたが、
途中からパニックを起こしてもいい環境づくりの視点で、地域の方や関わっている方に
説明していくというのも重要だとの意見がありました。
諦めるということも・・・
かかりつけの先生が諦めるということも当事者にとっては
いいことなんですよという一言をおっしゃったというお話が出てきました。
認知症の方ががんになった時のオペの方針
急性期病院ではオペをしていく方針になっていきますが、
その人の退院後の生活を考えると、特に食道系とか消化器がん、あるいは人工肛門を
作るようなケースでは、そちらの方が大変なことになるんじゃないかということで
お困りの事例が出てきました。
その中でもっと入院前の生活のことをしっかり丁寧に情報を収集していくことによって、
考え方が変わるのではないかと。
ただ情報提供書だけでは薄いので、関わっているかかりつけ医だけではなくて、
薬局あるいは介護関係者などからしっかり情報を取ることによって変わるんじゃないかと。
この事例を提供された方も確かにそういうことが起こってくる可能性があるので、
しっかりとそこのところを進めていくということでした。
医療者は患者の生活を邪魔する
私も半分医療者で半分がん患者なので仰っている意味がすごくよくわかりました。
いつもがんサポ喫茶ではぶっちゃけた話をさせていただいてます。