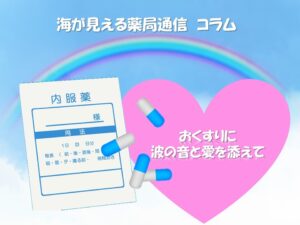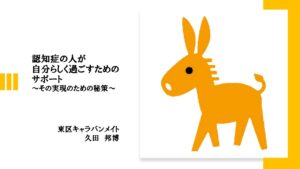
1000万人を超える「認知症サポーター」。それは日本が誇る巨大な「資産」です。 しかし、多くの地域で「サポーターを養成したものの、活動に繋がらない」「チームオレンジが“名ばかり”になっている」という悩みを抱えていませんか?
サポーターが「眠った資産」になってしまう最大の理由は、彼らが「何をすれば良いか分からない」「一人では何もできない」と感じているからです。
この記事では、その「眠れる資産」を揺り起こし、サポーターが「自分ごと」として地域づくりに参加する「生きたネットワーク」に変える、専門の「まちづくりファシリテーター」の役割と具体的な手法(ワークショップ)を解説します。
ワークショップの開催目的とは?
ワークショップの最大の目的は、**参加者の「意識変容」**です。
単に情報を集約したり、行政の計画を「伝達」する場ではありません。参加者一人ひとりが「自分も“まちづくり”の当事者である」と気づく(=自分ごと化する)こと。
そして、「私には何もできない」という“孤立”した思い込みから、「〇〇さん(別の参加者)となら、これなら出来るかも」という“協働”へのマインドセットに切り替えること。それこそが、私(久田邦博)が設計するワークショップの最大の目的です。
チームオレンジを推進するワークショップの特徴とは?
私のワークショップの特徴は、「対話」と「傾聴」をベースにしたプロのファシリテーションです。
私は「何か意見を言ってください」とは言いません。それでは「声の大きい人」の意見ばかりが集まってしまいます。そうではなく、**誰もが安心して「本音(不安や懸念)」を話せる「安全な場」**を設計します。
-
「認知症カフェをやりたいが、運営が不安だ」
-
「自治会の役員は、認知症に関心がない」
こうした「不満」や「不安」こそが、地域の「生きた課題」です。私はファシリテーターとして、その「本音」を「では、どうすれば解決できるか?」という**前向きな「行動計画」**へと、対話を通じて触媒(ファシリテート)していきます。
ワークショップの参加者に求められる役割とは?
参加者の皆様に、難しい準備は一切必要ありません。 「何かすごいアイディアを言わなければ」と気負う必要もありません。
私が参加者の皆様に唯一お願いしているのは、**「自分の地域の“困りごと”や“願い”を、自分の言葉で話してみる」**こと、ただそれだけです。
「もっとこうなってほしい」という「願い」を、「どうせ無理だ」という「諦め」に変えてしまうのが、対話のない地域です。 ファシリテーターとしての私の役割は、その「願い」を「具体的な一歩」に変えるお手伝いをすることです。
ワークショップの効果・成果とは?
ワークショップの最大の成果は、紙に書かれた「アクションプラン」そのものではありません。
最大の成果は、ワークショップが終わった後に**「参加者同士の“生きた”つながり」**が生まれることです。 「自治会のAさんが、認知症カフェのBさんと初めて話せた」 「推進委員のCさんが、自分たちだけでは無理だと思っていた課題を、サポーターのDさんに“ちょっと”手伝ってもらえることになった」
このように、「点」だったサポーターが「線」や「面」になる瞬間こそが、本当の「ネットワークの活性化」です。私のファシリテーションは、その「化学反応」を意図的に起こすためのものです。
1000万人のサポーターを「眠らせたまま」にしていませんか?
「サポーターは養成したが、活動に繋がらない」 「チームオレンジをどう動かせばいいか、最初の“一歩”が分からない」
その課題、**「対話の場」を設計するプロ(久田邦博)**が解決します。 行政主導の「やらされ感」のある会議から、住民やサポーターが「主役」になる“生きた”ワークショップへ。