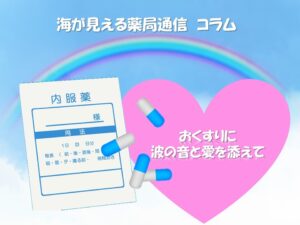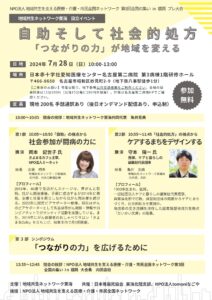認知症と地域共生社会の実現とは? がんサバイバー講師が語る「自分ごと」と「ウェルビーイング」【講演録】
「地域共生社会」という言葉が飛び交う中、認知症の方と共に、本当に安心して暮らせる地域をどう作ればよいのでしょうか?
先日登壇した「ちた医療介護ネットワーク研究会」では、「認知症と地域共生社会」というテーマで、私自身の経験と考えをお話しさせていただきました。
この記事は、その講演録です。 私自身が「白血病サバイバー」として死の淵から這い上がった経験と、「元製薬会社」として認知症分野に25年関わってきた専門的知見を掛け合わせ、「ウェルビーイング(より良く生きる)」と「アンコンシャスバイアス(無意識の思い込み)」の観点から、地域共生のリアルな課題と解決策を語ります。
講演録:「認知症と地域共生社会」の実現に向けて
皆さん、こんにちは。久田邦博(くにひろ)と申します。 本日は「認知症と地域共生社会」というテーマをいただきました。これは私への「挑戦状」だと受け止め、このテーマで準備をさせていただきました。
私は元々、製薬メーカーで認知症治療薬のことなどに25年関わり、情報発信や資料作成をする立場でした。同時に、慢性骨髄性白血病のサバイバーとして22年間、抗がん剤治療を続けています。
また、現在は「がんサポ喫茶止まり木」というオンラインコミュニティで、告知直後や再発直後の方の心のケア(ピアサポート)も行っています。
本日は、この**「①認知症の専門知識」「②がんサバイバー(当事者)の視点」「③ピアサポート(心のケア)」**という3つの視点を持ちながら、以下の構成でお話しします。
-
国が目指す「地域共生社会」と認知症基本法
-
私の体験:「死」を覚悟してから見えた「ウェルビーイング」な生き方
-
認知症の方の「本当の障壁」と、地域を変える「ぼっちゃ」の可能性
1. なぜ今「地域共生社会」なのか?国の本気度
「地域共生社会」という言葉は、厚生労働省が平成29年頃から「自分ごと・丸ごと」というキーワードと共に使い始めました。まさに「縦割り社会」をどう壊していくかが課題です。
特に認知症においては、2023年に「認知症基本法」が動き出しました。 この法律の正式名称には**「共生社会の実現を推進する」**と明記されており、国が本気でここを目指すという明確な意思表示です。
この法律の3番には「障壁(しょうへき)となるものを除去する」とあります。 この**「障壁」**とは一体何でしょうか?
私は、がんサバイバーとして、また認知症の方々と遊んだり旅行したりする中で、この「障壁」とは、**「地域の目」であり、「正しくない理解」、すなわち「アンコンシャスバイアス(無意識の思い込み)」**だと確信しています。
「認知症の人は何もできないのでは?」「記憶できないのでは?」 こうした思い込みは、支援者である私自身の中にもありました。
当事者グループ(日本認知症本人ワーキンググループ)も「希望宣言」の中で、「自分自身が囚われている常識の殻を破り、前を向いて生きていきます」と宣言しています。患者自身が持つ「常識の殻」すらあるのです。
私は当事者の方々と友達として付き合っていますが、LINEもできれば、飲み会もできます。私と何が違うのでしょうか? この「思い込みの壁」を壊すことが、共生社会の第一歩です。
2. 私の体験:「死」を覚悟してから見えた「ウェルビーイング」な生き方
では、病気や障害と共に「より良く生きる(ウェルビーイング)」とはどういうことか。私の体験をお話しします。
私は38歳で出世のことしか考えず働いていた時、突然「白血病」の診断を受け、「終わったな」という思い込みに包まれました。
治療法は「骨髄移植(リスクあり)」か「薬物療法(延命)」の2択。 当時、息子4人がまだ幼く、「せめて長男と酒が飲みたい」「父親として人生の荒波を伝えたい」その一心で、「目標生存期間を10年」と定め、可能性の高い「薬物療法(自己注射)」を選択しました。
しかし1年間は落ち込み、ただ息子のために生きる「やる気ゼロ」の日々でした。 ある日ふと気づいたのです。
「死ぬまでは生きている。どうせ死ぬなら、直前までくよくよしてるなんて馬鹿らしい。命が短くなるなら、1日を4倍速で充実させればいい」
そこから私の生き方は変わりました。研修部門の仕事を2時間で終え、残りの6時間は自分の技術を高めるために費やしました。 「患者が語る医療接遇研修」を病院に提案し、それが口コミで広がり、全国800所以上で講演するようになりました。
そして、目標だった10年目を迎えたその日。 ホテルのベッドで深夜に目が覚め、強烈な吐き気と下痢に襲われ「あぁ、僕は死ぬんだな」と思いました。
救急車を呼ぼうとした時、「10年生きたいと神頼みまでした自分が、10年経った日に命乞いをしていいのか? 今日は感謝と祝福の日だ」と思い直しました。 「満足した人生だった。ありがとうございます」と合掌して眠りに着きました。
幸い翌日も元気に目覚めましたが、私はこの経験で**「自分らしく生きていると、安らかな最後を迎えられる」**と悟りました。
この経験を、今度は告知直後のがん患者さんたちに伝えています。 毎週木曜に「がんサポ喫茶止まり木(患者会ではなく喫茶店)」というオンラインの場で、皆でバカ騒ぎをするのです。 告知直後で落ち込んでいた方も、2〜3回来るうちに立ち直り、今度はサポートする側に回っていきます。
3. 認知症の方の「本当の障壁」と、地域を変える「ボッチャ」の可能性
私は企業の在職中から、若年性認知症の本人・家族交流会に参加していました。 一緒にビアガーデンに行き、ソフトボールをし、遊ぶ中で、自分が持っていた「認知症」への間違った思い込み(メガネ)がガラガラと落ちていくのを感じました。
しかし、コロナ禍でその会が1年近く開催できなくなりました。 久しぶりに開催された時、私が見た光景はショックなものでした。私の友人のほとんどが、もうそこに来られない状態になっていたのです。
エビデンスはありませんが、私は**「社会活動(つながり)が、認知症の進行抑制に大きく影響している」**と肌で実感しました。
では、どうすれば「つながり」を作れるか? 認知症カフェを回りましたが、当事者が集まらない、あるいは「無理やり連れてこられてつまらなそう」という現実も多く見ました。
そこで私が今、注目しているのが**「ボッチャ」**です。
「ボッチャ」は、元々障害者の方向けに作られたスポーツで、ルールは簡単、誰でもできます。 地域のサロンやコミセンで「ボッチャ」をすると、60代から90代の方が即席でチームを組み、夢中になって換声を上げ、知らない同士が一気に仲良くなっていきます。
-
行きたくなる場所(楽しい)
-
夢中になれること(没頭)
-
つながり(人間関係)
「ボッチャ」は、ウェルビーイングの3要素(PER)を全て満たします。 認知症の方も、障害を持つ方も、地域の住民も、みんな一緒にできる。 これこそが、アンコンシャスバイアス(障壁)を壊し、地域をつなげる最強のツールではないかと企んでいます。
私はこれからも、人と人をつなぐ「赤帽子の存在」として活動していきます。ご清聴ありがとうございました。
「当事者視点」の研修で、組織の「壁」を壊しませんか?
「認知症の方への“思い込み”をなくしたい」 「縦割り組織を越えて、地域やチームの連携を強化したい」
本講演で語られた「アンコンシャスバイアス(無意識の思い込み)」の除去や、専門知識と当事者視点を掛け合わせた「ウェルビーイング」な生き方の提案は、久田邦博の研修の核心です。